「コンフォートゾーン」を抜け出して、成長の機会に



「部下が育たない」。マネジメントの課題として、上司(評価者)の嘆き節があちらこちらで聞こえてきます。互いの「思いは通じない」と、コミュニケーションのススメを以前コラムで書きましたが、今回は「目標」自体を明確にしているかという話。
上司の視点ではメンバーは「あれもこれも、できていない」という評価をしています。部下からすると、「こんなにやっているのに、上司は見てくれていない」との言い分。お互いに視点のズレができているケースがよくありますね。実は、「やっている、やっていない」という「個別目標」とその「到達点」が、上司、部下とも曖昧になっているケースが少なくありません。目標設定は、ほとんどの企業でやっていると思いますが、細かいところまでしっかり明確にしているか。まずはここに課題が潜んでいます。
そもそも、①、「何を目標としているのか。ここがズレているケース。もう一つ、②、どの程度やれば、評価される・されないのかの基準。そして、③、上司(評価者全員)、部下でその共通認識を持ったかどうか。
②、についてもう少し。目標設定では個別目標について、S、A、B評価とかあるかと思います。では具体的にSの基準はどこまでやればSなのか。同じくA、Bの基準は上司と部下で一致しているのか。営業であっても数字の100%達成はわかりやすいですが、その上のSの評価はどうなのか。未達でもどの程度未達なら、評価がどうなるのか数値で正しく設定しているのか。
数字に表しにくいと言われるスタッフ部門の目標も同じく。「スタッフ部門は目標設定ができないので。。。」、と曖昧なままにせず、どこまでならSなのか。A基準はどうなのか。事業の数字に何かしら貢献しているはずなので具体的にわかるように例えば数値を用い、期初の目標設定スタートのタイミングで認識を合わせないといけません。期初に立てた目標が「・・・について完遂します。」だと言葉が抽象的なので、期中の進捗でも、上司、部下の到達度の意識が乖離して、マネジメントしようにもできないということになりかねません。これではPDCAマネジメントを機能化できません。お互いの認識にズレがあるので上司と部下の距離が離れたままになってしまいます。
何を部下にやってもらうのか。どれくらい(の程度)やってもらうのか。日々のマネジメントでも、何の仕事から優先してやってもらいたいか上司、部下で明確になり、上司は部下へ具体的なアドバイスもどのくらい、どうやってやるのがいいのかがイメージできるのです。マネジメントは育成だと言いながら、どこまで部下を育成するのか。どっちの方向へ?どの程度?を上司自身のためにもはっきりさせるということです。
目標設定がしっかりできていれば、マネジメントのPDCAを回すこともできますし、単なるタスク作業を部下にやらせるとはならずに育成にもつながる。評価も上司、部下の認識が合致しているので、納得度が高まります。結果として、PDCAマネジメントが機能化できるのですね。そのためにもスタートは「目標設定」を明確にする。マネジメントがぐるぐる回る第一歩と言えます。
逆に言えば、「上司力」を探るには、部下の目標について各論で答えられるかがポイントと言えます。なぜその目標を持たせるか?どんな目的があるのか?どの程度でハイ達成、未達成?部下にどう関わるのか?できる上司は、自分の部下の「具体的な目標」をすらすら答えてくれるはずです。
事業の前進、個人・組織の育成を人生のテーマに、お客様の懐に深く入り、ハンズオンで事業の発展、改革に関わっていきます。四国のお寺巡りをやっております。そんな話もどうぞ。

「採用成功には、採用ターゲットに刺さる自社の魅力を明確にすることが重要です」。正直、耳にタコができるほど聞く言葉です。とはいえ、…


人材獲得競争が年々激しくなる中、「採用マーケティング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。求職者に「選ばれる企業」となるた…

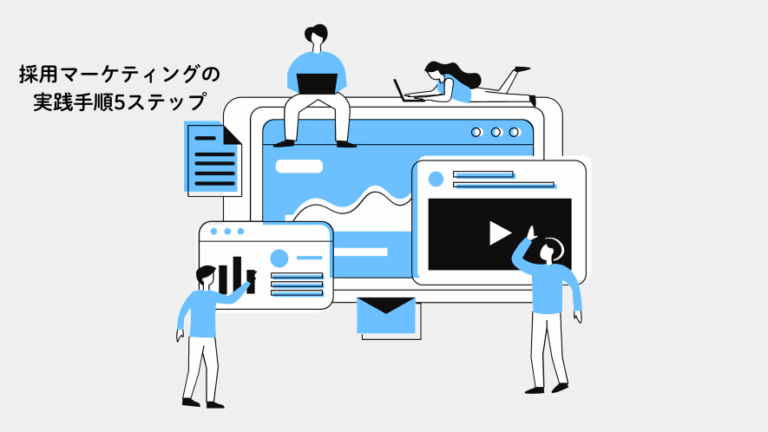
売り手市場が続く採用市場。母集団形成や内定承諾後の辞退は、多くの企業にとって悩みの種といえます。これらの採用課題を解決するために…


ふわっとした悩みから、明確な課題まで。採用力に関することは、何でもお気軽にご相談ください。