新人育成を新人研修だけで終わらせないように。



サッカーの戦術論を企業経営における組織論のヒントにするケースが増えてきていますね。
(私の感度がそこにやたら高く向いているだけかもしれませんが)
サッカーの戦術論の一つに、組織論に通じる面白い定義があります。
それは、「サッカーとはカオスである」というものです。
“カオス”とは、一般的に「混とんとした」という意味で使われることが多いと思います。
ですがここでは、「初期設定のわずかな違いが、事前の予測を大きく覆すような結果を生む複雑な事象」のことを指しています。
サッカーにおける選手の技術や体力、戦術などの一つ一つの細部の事実は把握できますが、サッカーの本質はそれ以外の多くの構成要素が相互に影響を及ぼし合っている複雑な事象と考えられます。
例えば、相手を抜く技術を持っていたとしても、相手がいつ、どちらに動くかは予測できません。
小さな小石があって、ボールがイレギュラーしてしまうこともあります。
ベンチの監督から「行け!」と声がかかり、その声に敵も味方も惑わされる可能性があります。
そのため、各構成要素(技術、体力、精神力、戦術など)の理解は必ずしもサッカーという全体の理解には繋がりません。
サッカーは、各構成要素が相互に影響を及ぼし合う複雑な事象と認識し、複雑なものを複雑なまま扱う力が必要とされます。
いかがでしょうか?
このサッカーの戦術論における定義と同様に、組織を定義してみると、共通点とともに組織運営の手掛かりが見えてきます。
常に組織が置かれている状況は変化しているのに、その初期設定の違いに着目することはできているでしょうか。
初期設定の違いが組織にどのような影響を及ぼすのか、それを認知し、扱うことはできているでしょうか。
例えば、事業環境の変化、競合の動向、顧客のニーズの変化、異動や退職による人材の入れ替わり、人員の増減、メンバーの能力成長、精神状態等々。
このような初期設定の変化を扱わずに、これまで通りに組織を動かそうとしているケースを多く見かけます。
組織はカオスである。
この前提に立って組織と向き合うことは、これからの組織運営を考えるヒントになるのではないかと思います。
大切にしていることは、その組織や人が見てきたものと同じ景色を見ること。その上で今後の仕組みを作ること。仕組みとはいえ、人間っぽさを捨てないこと。サッカー大好き。企業内でサッカー的組織創りに挑戦したいです。興味のある方はご一緒に!

「採用成功には、採用ターゲットに刺さる自社の魅力を明確にすることが重要です」。正直、耳にタコができるほど聞く言葉です。とはいえ、…


人材獲得競争が年々激しくなる中、「採用マーケティング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。求職者に「選ばれる企業」となるた…

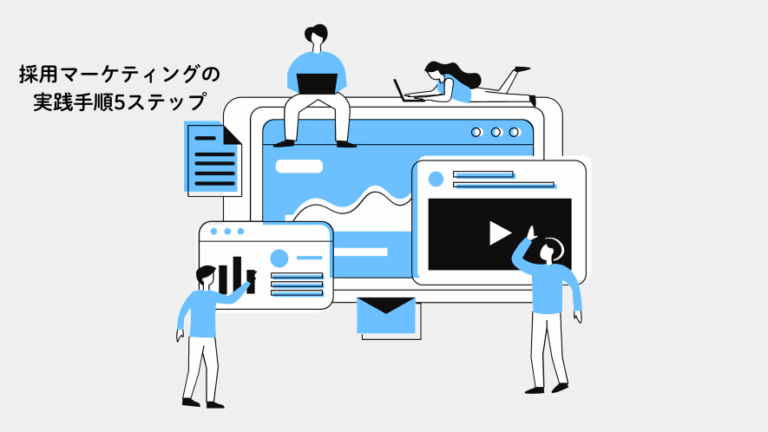
売り手市場が続く採用市場。母集団形成や内定承諾後の辞退は、多くの企業にとって悩みの種といえます。これらの採用課題を解決するために…


ふわっとした悩みから、明確な課題まで。採用力に関することは、何でもお気軽にご相談ください。