上手く波にのれている??リモートワークでストレスレスに仕事を進める3つのポイント



我が家の小学生の娘は、時々学校に行きたくないという日があります。
その度に理由を聞くのですが、授業そのものだったり、先生や友達との関係だったり、色々あります。
先日担任の先生との面談でそのことについて相談したところ、こんな回答が返ってきました。
「色々な子がいるし、学校が大好きな子もいれば、そうでもない子もいる。その子のペースで好きな部分(例えば給食、体育だけは好きだから学校に行くでOK)を見つけて学校に来てくれればいいと思います。あとは、心が弱っていると、ちょっとしたことでもマイナスに受取ってしまうこともあるから、リフレッシュのためにたまには休んでもいいんじゃないですかね。」
ということでした。
私自身、「学校へは行かなければいけないもの。」 「みんなと同じにできないことはよくないこと。」という思い込みがどこかでありましたが、子どもそれぞれの個性や、感性を認めてくれるその先生の回答を非常にうれしく感じました。と同時に、「そう感じるうちの子はちょっと変わっているのかしら?」と思いながらも、その違和感を口に出したことで、親としての子どもへの対応も明確になり、新しい発見があったことが非常によかったです。
この一件を通じて、それぞれの人が感じる違和感は、正解不正解、いい悪いもなく、それをお互いに尊重し合い、よりよい関わり方をお互いに模索してくのがあるべき姿なんだな、ということを改めて教えてくれたような気がします。
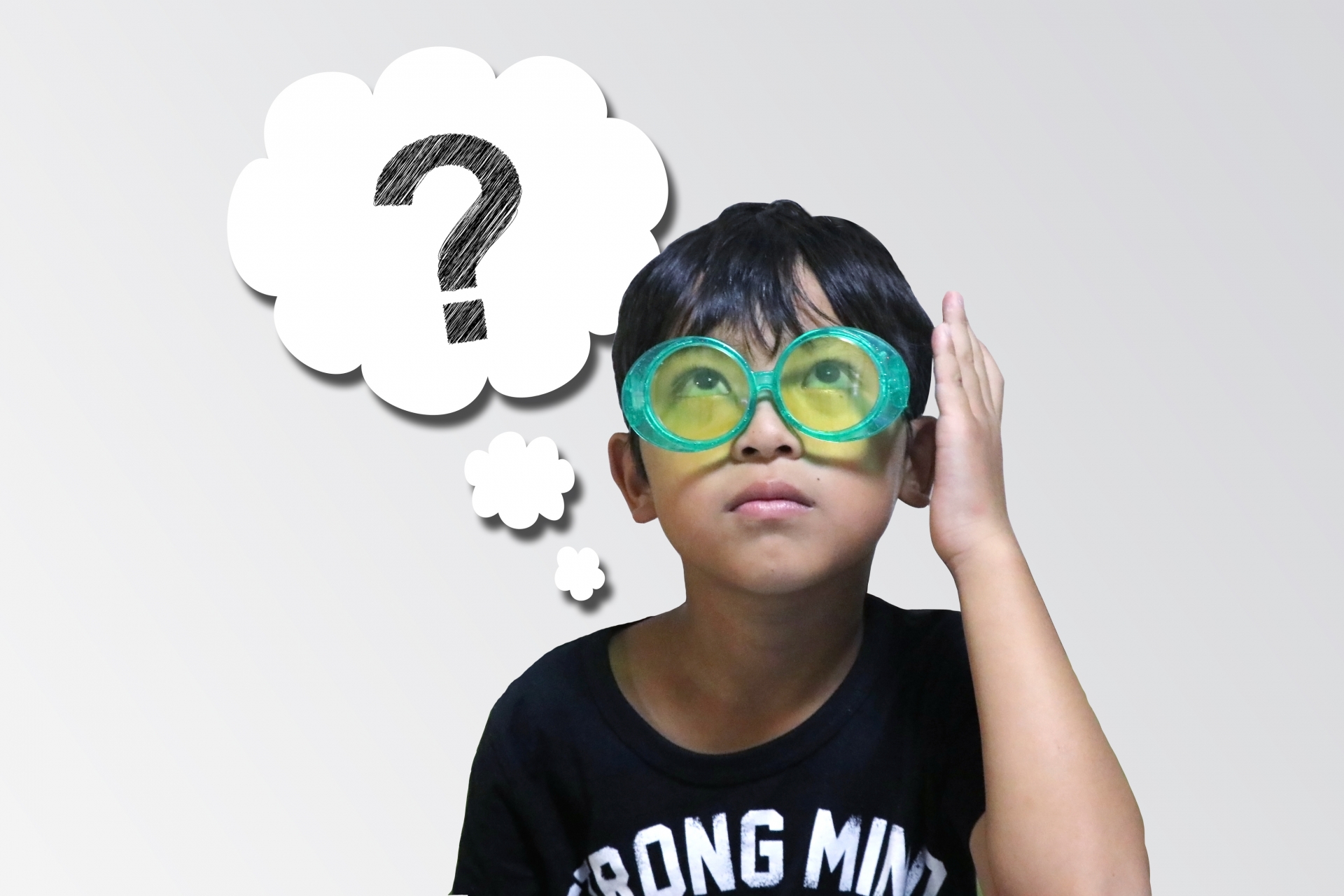
これは、会社組織、仕事に置き換えても同じだなぁと感じます。
違和感を誰も口に出さない組織だと、お互いに新しい発見も出てこなくて、今までのやり方、今までの考え方が「正解」となってイノベーションが生まれなくなってしまいます。
違和感を口に出しやすい雰囲気を組織として作っていくことも大事ですし、一人一人が違和感のセンサーを磨いていくことも大切だと思います。特に東京に暮らしていると、満員電車、人混みなど、違和感にいちいち反応していると逆に感情をすり減らすことになるため、知らず知らずのうちに自分自身のセンサーをシャットダウンしてしまっている気がします。その事実を受け入れて、時には立ち止まって、自分の中のセンサーの感度をあげることも大切だなと感じました。

「調和のとれた社会づくり」というビジョンに向かって、働く一人ひとりが強みを発揮できる組織づくりをめざしています。また、一人でも多くの女性が活き活きと働ける社会をテーマにした活動も広げています。プライベートでは三児の母。

「採用成功には、採用ターゲットに刺さる自社の魅力を明確にすることが重要です」。正直、耳にタコができるほど聞く言葉です。とはいえ、…


人材獲得競争が年々激しくなる中、「採用マーケティング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。求職者に「選ばれる企業」となるた…

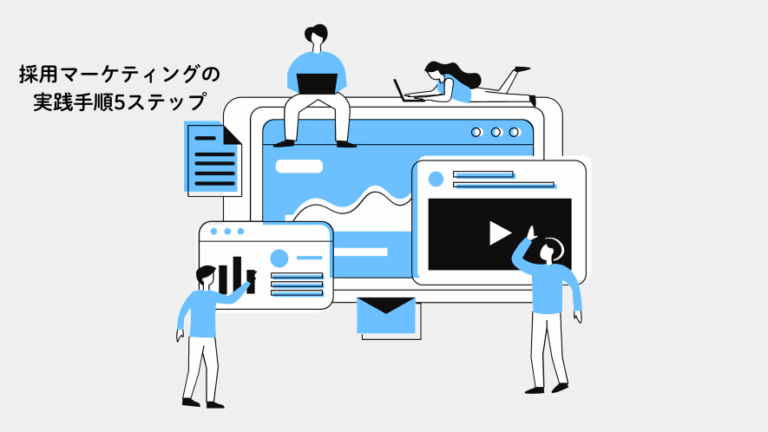
売り手市場が続く採用市場。母集団形成や内定承諾後の辞退は、多くの企業にとって悩みの種といえます。これらの採用課題を解決するために…


ふわっとした悩みから、明確な課題まで。採用力に関することは、何でもお気軽にご相談ください。