採用計画・採用戦略立案のポイント(ダウンロード資料あり)



ターゲット人材の「体感」を通して「共感」と「感動」を呼ぶ。
はたして、この要件を満たした会社説明会を実施できている企業はどの程度存在しているでしょうか?
会社説明会に頼らずとも応募者に「体感」「共感」「感動」の機会を提供できているのであれば、その企業にとって会社説明会は必須プロセスではありません。
しかし、それができていない、或いはできているかどうかに不安が残るのであれば、会社説明会は必須プロセスであり、且つその内容に改善の余地があると考えるべきでしょう。
前回(「会社説明会」の終焉)、採用成功につながる説明会のキーファクターとして「ストーリー設計」、「シナリオ熟成」、そして「五感への訴求」の3点をご紹介しました。
もとい、「キーファクターは3点ありそうですよ」という、もったいぶったご紹介止まりでしたので、今回はその各ファクターの内容について整理してみたいと思います。
ここで言う「ストーリー設計」には、狭義と広義があります。
狭義には、説明会の開始から終了までのコンテンツと流れを考えること。
広義には、採用活動全体における説明会の位置づけや役割を定義することを意味します。
ここではまず、広義の意味でのストーリー設計から着手すべきでしょう。
求職者にとって、その企業に関する情報源は、採用サイトや採用パンフ、或いはリアルな社員との接点など、説明会の前後を取り囲むように複数存在します。
果たして、そのすべての情報源に一貫性と連動性が感じられる説明会と、そうではない説明会、どちらが戦略的で効果的であるかは自明の理であると思います。
つまり、説明会単体でコンテンツや流れを作り込む前に、求職者とのコミュニケーションポイント全体を俯瞰しながら、説明会の位置づけや役割をまずはじめに考えるべきであるのです。
採用活動を通して一貫したメッセージ(理念、ビジョン、採用コンセプト、ビジュアルなど)を説明会の根底に織り込みながら、一方で「参加して良かった!」と求職者に実感してもらえるような、その他の情報源との相互補完関係を担保できる説明会を綿密に設計しましょう。
ここではプレゼン技術ではなく、説明会の準備段階で如何にプレゼン品質を上げることができるかについて考えてみます。
狭義の意味での「ストーリー設計」です。
ひとつひとつのパーツを、有機的に紡いでシナリオを熟成させておくこと。そのためにひとつおすすめの方法があります。
まず、現行の説明会で使用しているプレゼン資料を見ながら、各ページのコンテンツとポイントを端的に書き出してリスト化します。Excelなどを活用すると整理し易いですね。
たとえば50ページのプレゼン資料であれば、50行のリストが出来上がります。
リストが出来たら、次はこのリストをじっくり観察しながら検証します。
「なぜこのページはここにあるんだろう?」
「なぜこのページの次がこのページなんだろう?」
「そもそもこのページでは何を伝えたかったんだろう?」
少なからずきっとこのような疑問が生まれるはずです。
その疑問を解消できるよう、リスト上でページの配列を並び替えてみるのです。
その過程で、現行の説明会で不足しているページや、逆に余剰なページも発見することができます。
説明会の「解体」と「再構築」、ぜひ一度やってみてください。
最適化したストーリーとシナリオを求職者の心に届けるため、表現方法にも心を砕きましょう。
説明会は「理解」ではなく「共感」と「感動」を目指したいものです。
ここでも、プレゼン技術というよりも設計の観点で考えてみます。
また、誰でも容易に想像ができる「現場社員の協力」という手段についても敢えてここでは外します。
1. シンプルな表現
プレゼン資料はシンプル・イズ・ベストです。言い換えれば、プレゼン資料を賑やかにし過ぎないよう注意が必要です。
賑やかとは、文字量やアニメーションの多用を指します。
文字量が多すぎたり、アニメーションが多用されたプレゼン資料では、本来伝えたいメッセージの核心を視覚的にインプットすることができません。
「このページのメッセージは一言で言うとこれだな」、と求職者が視覚的に直観で把握できるようにしましょう。
2. 情報の一般化
情報は、求職者が想像し易い次元の表現や例え話に置き換えられるよう、引き出しを十分用意しておきましょう。
人は基本的に自分が経験したこと以外のことを想像するのは不得手であると言われます。
それを逆手に取って、多くの求職者がこれまで経験したことがあるであろうシチュエーションになぞらえて例示してあげることで、「あぁ、そういうことか」と求職者の経験的記憶と接続してあげるのです。
3. ベネフィットの明示
説明会で提供するひとつひとつの情報に、それは求職者にとってどんなベネフィットがあるのか、具体例を揃えて明確にしておきましょう。
つまるところ、多くの求職者は「それは自分にとって何が嬉しいか」という基準で情報の有益性を判断します。
説明会で提供される情報についても同様です。どれだけ網羅的に情報提供ができても、結果的に求職者をワクワクさせられなければその説明会は失敗なのです。
4. 求職者の当事者化
求職者を傍観者にさせないためにはどうすれば良いか?それは「聞く」だけではない「体験」の場を提供することです。
インターンシップほどの時間的自由度は確保し難いとしても、説明会の中で求職者が当事者として「考える」「動く」場面を少しでも作ることができないか考えてみましょう。求職者同士でちょっとしたワークに取り組んでもらうだけでも、従来の説明会と大きく違いを生み出すことが可能です。
5. 動画の活用
採用コンセプトや社員の声、働きぶりなどを動画を通して体感してもらえれば、求職者の「共感」と「感動」を呼ぶ効果は絶大です。
人は「光・音・映像」に心が揺さぶられ、強く記憶に刻み込む生き物です。昨今はとりわけ若年層において就職活動に限らず動画に対する親和性が非常に高くなっているという時代背景もあります。
上記4つの手法と異なり、それなりの投資が必要な施策になりますが、説明会参加者の選考移行率を向上させる有効な手段であることは確かです。

前回、今回と会社説明会をテーマとして考えてきましたが、皆さまが自社の採用活動の惰性や慣性に対して疑問の念を抱くきっかけだけでもご提供できたのであれば幸いです。
戦略性と意図性のある採用活動を実現することで、企業価値を向上させる。私たちはそれが使命であると考えていますし、皆さまにも同じスタンスで自社の採用活動に向き合ってほしい。
そんなクライアント様と、もっといい仕事をしていきたいなあ、と春の到来を感じて少しワクワクドキドキしながら独り思う夜なのでした。
【関連記事】
「会社説明会」の終焉
「何が目的か、何が手段か」に拘ります。顧客以上に顧客好き、はもう治りません。論理派気取りで情緒的、寂しがりやの一人旅、早起き苦手な山登り、真面目な顔してヘヴィメタル、強くもないのにお酒好き。典型的な天邪鬼ですが、実は褒められて伸びるタイプです笑

「採用成功には、採用ターゲットに刺さる自社の魅力を明確にすることが重要です」。正直、耳にタコができるほど聞く言葉です。とはいえ、…


人材獲得競争が年々激しくなる中、「採用マーケティング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。求職者に「選ばれる企業」となるた…

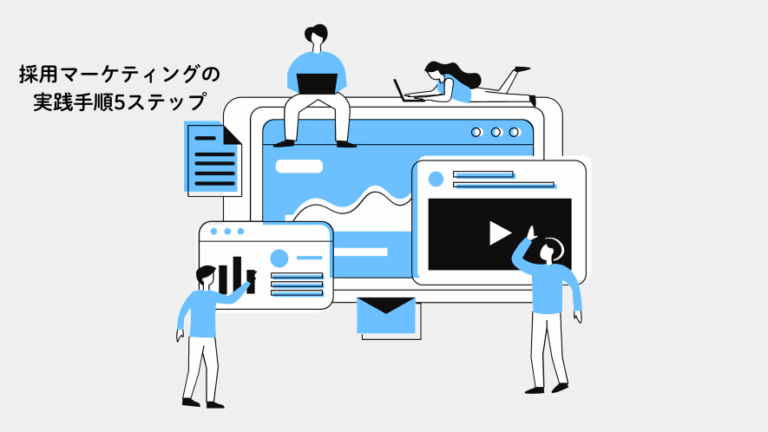
売り手市場が続く採用市場。母集団形成や内定承諾後の辞退は、多くの企業にとって悩みの種といえます。これらの採用課題を解決するために…


ふわっとした悩みから、明確な課題まで。採用力に関することは、何でもお気軽にご相談ください。