採用ブランディングとは?実践に欠かせない5つのステップを解説!



盛り上がるコンテンツマーケティングの中、実際のコンテンツがつくれなくて悩むみなさん、多いですよね?記事をアップしないといけないのはわかっているけど、他にもやることは盛りだくさん。気合だけでコンテンツを創ることはできません。コンテンツマーケティングをやるためには体制が重要。そういうお話です。
計画的なコンテンツマーケティングのためには、きちんと設計されたPDCAを回せる体制を作ることが大切です。しかもこのPDCAは他のいろんなものに比べてスピードが早い。だから、常に何をPLANし、どのようにDOし、何をCHECKし、いかにACTIONするのか、を決めてから進まないと「グダグダ」な結果になります。ロクにナーチャリングもできないまま、コンテンツを創ることが目的化したり、何も手入れをしていないのに分析だけが仕事になったり、ムダをたくさん生み続けることになり、関係者の疲労と無力感だけが残ります。
最初にやるべきは4つです。
・適切な目標設定
・目標設定にあわせたロードマップ
・動きの把握と分析をするチェック体制
・コンテンツを安心して回せる運用体制
これに尽きます。
では、これをどうやればできるのか?編集長とディレクターとマーケター。これらの役割を担える人材が集まった編集部を作ることです。社内人材ですべてをまとめるか社外人材に頼るか、それはそれぞれの状況にあわせてで良いと思います。ただし、コンテンツマーケティングに知見のない人がいないとしたら社内社外をミックスした体制で進行することをおすすめします。
コンテンツマーケティングには強力なコンテンツ力とユーザーの心を知っている、またはつかむための客観性が必要不可欠です。自分たちが売りたいものや伝えたいことは当然社内人材の方が良く知っています。高い専門知識がないとPRするための素材が生み出せません。一方でそれらの専門知識がどのように伝えればきちんと伝わるのか、届くメッセージとして発信できるのかは、発信者の事情や現実とは別の所で世の中のニーズやトレンド、市場の状況を知っている方が、刺さるメッセージを送り出すことに長けた存在となるでしょう。そういう意味で編集部内に社内人材と社外人材をミックスした体制をつくることは成果につながりやすい人材戦略かと思います。
コンテンツの企画は編集部内で、まず誰に何を届けるのかを議論するところから始めます。何を当たり前のことを、と思うかもしれませんが、誰に(ターゲット)が曖昧だったり、何を(受け手の期待)がぼんやりしていると刺さるコンテンツは生み出しづらくなります。ターゲットと期待が設計できたら、コンテンツです。コンテンツは一定周期でどのようなコンテンツを綴っていくのかを事前に計画しておきます。そうでないと今週記事アップしないといけないのにまだ何も考えてない!と焦ること必至です。ここまで来たらあとは役割分担すればOKです。

コンテンツ運営がはじまったら、効果分析と改善です。つくって、分析・検証して、改善して、つくる。このPDCAがすべてです。何をどう改善すれば効果が出るのか。「良くなった!」を積み上げましょう!「よくなった!」と感じる瞬間がないと、これやって意味あるの?という疑念が溜まる。そして、次の打ち手に不安が残り、足が止まる。こうなると何もうまくいくはずがありません。プロセスの中に小さなゴールをいっぱいつくって、ひとつずつクリアしていく。まずは5,000PV、次は3万PVとか。月間問合せ10件をまずは20件にとか、ユーザー数3,000を20,000にとか。編集部(マーケティング担当)の存在意義を照らしわせて、自分たちの取り組みに最適な指標を見つけて、立ち向かう。コンテンツマーケティングのPDCAの肝はこの「良くなった!」です。
SEOやらナーチャリングやらWEBライティングのコツやらいろいろとミックスして複雑化するマーケティング。難題だから面白い、と深く思う今日このごろの安井でした。
組織活性につながるクリエイティブとは何か?問題の本質は何か?を追求する毎日。近道でも回り道でもゴールに繋がるプロセスを大切に、現実にも夢にも向き合いたいと思っています。二地域居住の週末田舎暮らしやってます。

「採用成功には、採用ターゲットに刺さる自社の魅力を明確にすることが重要です」。正直、耳にタコができるほど聞く言葉です。とはいえ、…


人材獲得競争が年々激しくなる中、「採用マーケティング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。求職者に「選ばれる企業」となるた…

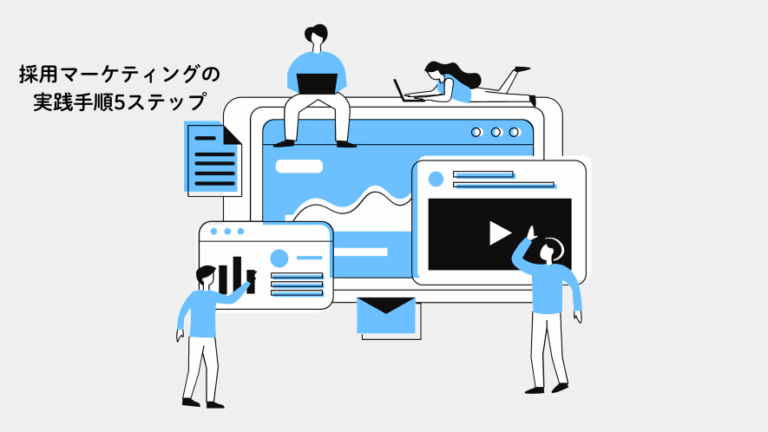
売り手市場が続く採用市場。母集団形成や内定承諾後の辞退は、多くの企業にとって悩みの種といえます。これらの採用課題を解決するために…


ふわっとした悩みから、明確な課題まで。採用力に関することは、何でもお気軽にご相談ください。