採用コンセプトは、「かっこよさ」より「使いやすさ」。



3月1日、就職ナビOPEN。いよいよ新卒採用が正式にスタートしますね。この日に向けて採用サイトや入社案内などを、ギリギリまで制作している企業さまや採用サービス会社はとても多いと思います。実際、僕もその一人です。2月末納品が山のように重なり、この冬はプライベートな時間はほとんどナシでした…。でも、それもうれしい悲鳴ですよね。そもそも今つくっている制作物のほとんどが、クライアントがコンペ(数社による競合プレゼン)でジャンプを選んでくださったおかげなわけですから。
とはいえ、毎年たくさん参加しているコンペ。お声がけいただくこと自体とてもありがたいことですが、正直な話、モチベーションが上がるコンペとそうでないコンペがあります。なんだかんだで業者も人間ですので…。コンペの主催者側としても、モチベーションの高い業者から素晴らしい提案がほしいものですよね。ということで、非常に僭越ながら、自分自身の経験を振り返って「やる気が出るコンペって、こういうコンペ」をまとめてみました。
競合が7社も8社もあると、やっぱり「どうせ提案しても選ばれるわけないよな…」と最初から弱気になり、本気になりにくくなってしまいます。でも、3社や4社程度のコンペなら違います。提案次第で、何とかなるかも!と希望が持てます。「数ある候補業者から、ホームページの実績とかを見て、選定してお声がけしてくれたのかもしれない!」と、勝手に想像してやる気を出たりもします。
悩んでいる人を見ると助けたくなりますよね。それ、コンペでも同じだと思います。クライアントからストレートに悩みや課題をぶつけられると、何とか解決したくなるものです。また、悩んでいるクライアントほど課題について深く考えているので、オリエンテーションのポイントも明確で、本質的な解決策が求められることが多く、提案者としては燃えてしまいます。
クライアントの熱意にも、モチベーションは左右されてしまうものです。担当者だけでなく決定者の方が同席し、オリエンテーションで直接、コンペにかける想いとポイントを話してくださる。こちらからもプレゼンで直接、提案をぶつけることができる。そんなコンペであれば提案に熱意が乗ることはもちろん、決定者—担当者—提案者間の伝言ゲームもなくなるので提案の精度も上がります。
オリエンからプレゼンまでの間に、「御社のことをもっと知りたいので、追加のヒアリングをさせてください」「プレゼンの前に方向性を提案し、議論したいので、一度、打ち合わせをお願いします」など、イレギュラーなアポイントを依頼することがあります。あえてオリエン→プレゼンという規定のプロセスにはない、競合他社がやらない「抜け駆け」をお願いするのは、より良い提案したいからです。そのために、全社横並びのプロセスである必要はないはず。こちらの熱意に応えてくれるクライアントの仕事は、やはり燃えるものです。
課題に真剣に取り組み、かつ競合他社にはない提案をしようとアイデアを練ると、どうしてもオリエンの内容を超えたボリューミーな提案になったり、オリエンの内容とちがった提案になってしまうことがあります。そのため、「オリエンの内容だけにしばられることなく、ぜひ新しい提言やちがった角度からの提案もほしい」なんて言葉をあらかじめいただけると、発想の幅が広がり、その期待にも応えるために、あれもこれもとたくさん考えたくなります。
上記の5つの他にもまだまだ色々出てきそうですが、やっぱりどの項目にもその根底には「クライアント—業者」という対向関係を超えて、同じ悩みを共有し、二人三脚で解決していくパートナーでありたい、課題の当事者でありたい、という気持ちがあるのだと思います。実際、そういう想いをしっかりと提案に乗せることができたコンペは、勝って来れた気がしますし、良い仕事になっていった気がします。今後もこの想いを大切にし、やる気全開でコンペに向かう次第でありますので、全国の企業さま、お声がけのほど何とぞよろしくお願いします!
ジャンプがこれまでに行ってきたソリューションの事例をまとめました。課題解決のパートナーになり得るかどうか。ぜひ、ご参考ください。
じっくりとヒアリングを繰り返し、課題発見、企画提案から取り組む「対話型モノづくり」を信条としています。クリエイターである前に、信頼できる相談相手でありたい。最近始めた野球では、長打が打てるようになりたいとバッティングセンターに通う日々です。

「採用成功には、採用ターゲットに刺さる自社の魅力を明確にすることが重要です」。正直、耳にタコができるほど聞く言葉です。とはいえ、…


人材獲得競争が年々激しくなる中、「採用マーケティング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。求職者に「選ばれる企業」となるた…

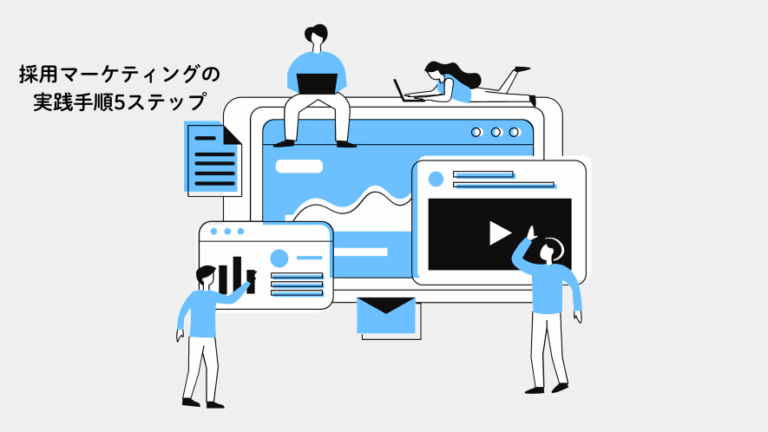
売り手市場が続く採用市場。母集団形成や内定承諾後の辞退は、多くの企業にとって悩みの種といえます。これらの採用課題を解決するために…


ふわっとした悩みから、明確な課題まで。採用力に関することは、何でもお気軽にご相談ください。