パソコンを使えない若者が増殖中

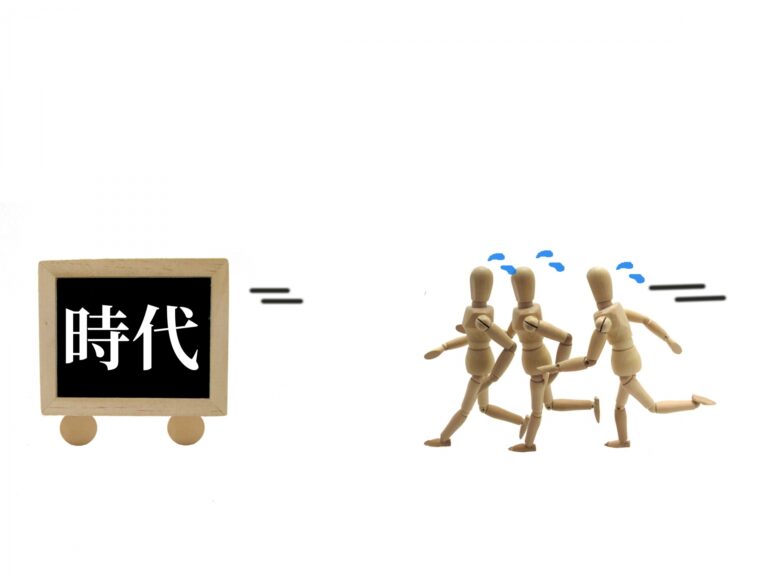

受講者から「いやーすばらしい研修だった」という感想が漏れる研修は、いい研修に見えますね。受講者アンケートに、そんな賞賛があふれているようであれば、主催の人事担当者も評価されますし、次年度も継続受講でというストーリーが見えてきそうです。しかし、受講者の評価が高い研修は、本当にいい研修と言えるのでしょうか。受講者による評価がある一方で、経営者は何を気にするかと考えると、業績などの成果に結びついているかだと思います。成果に結びつかないのであれば、いくら受講者が賞賛しようとも、経営者はその研修を決して評価しないでしょう。成果は行動によってのみもたらされます。研修を境に、受講者の行動に変容が見られないのであれば、成果に結びつくことはありません。受講者が高評価を付けることがすなわち、彼らが翌日からそれまでと異なる行動をし始めることにはならないのです。高評価だったその記憶も日々の業務の中で薄れていき、やがて何もしなかったのと同じ日常に戻ってしまいます。これはいつの世にもよく見受けられる一般的な現象と言えます。
研修の質を決定する要因は、一般的に2つあると言われています。一つは「コンテンツ」、もう一つは「講師」です。優れた研修コンテンツを優れた研修講師が実施することが、いい研修の条件ということです。しかし、この一般論だけでは、実際に成果に結びつくことは少ないというのが私の実感です。それは、前項でも述べたとおり、世の研修の多くが「やりっ放し」になってしまうからです。では、成果に結びつけるような行動変容はどのようにしたら起こすことができるのでしょうか。それはやりっ放しにしない仕掛けをつくること、すなわちフォローを機能させることです。具体的な例としては、フォロー研修のような場を後日設定し、受講者がそこに向けて「成果目標」とそのための「行動計画」を立てて、その実現を宣言することによって、行動変容をうながすというものです。宣言する対象は、その研修の受講者たちだけでなく、直属の上司や同僚たちも含めた方がよいでしょう。そうすることで、フォロー研修の日までにやっておかなくてはならない日々の行動を、周囲の人たちもまた支えてあげることになり、成果に結びつきやすくなります。優れた研修講師による優れた研修コンテンツを実施する研修会社はたくさんあると思いますが、できることであれば後日のフォロー研修まで視野に入れた設計をされることをオススメいたします。
前職は人事を担当。会社全体の仕組みから社員一人ひとりのケアまで、幅広い視点から会社や組織の活性化に貢献します。既存の概念にとらわれることなく、常に柔軟に考えることを心がけています。趣味は料理。食べるのも作るのも大好き!

「採用成功には、採用ターゲットに刺さる自社の魅力を明確にすることが重要です」。正直、耳にタコができるほど聞く言葉です。とはいえ、…


人材獲得競争が年々激しくなる中、「採用マーケティング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。求職者に「選ばれる企業」となるた…

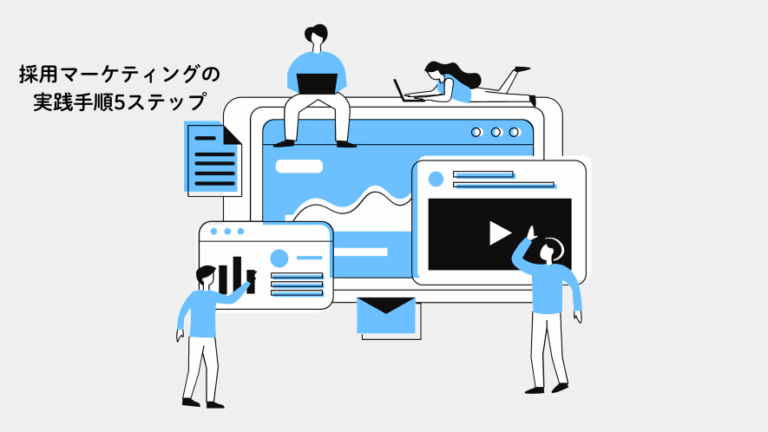
売り手市場が続く採用市場。母集団形成や内定承諾後の辞退は、多くの企業にとって悩みの種といえます。これらの採用課題を解決するために…


ふわっとした悩みから、明確な課題まで。採用力に関することは、何でもお気軽にご相談ください。