パソコンを使えない若者が増殖中

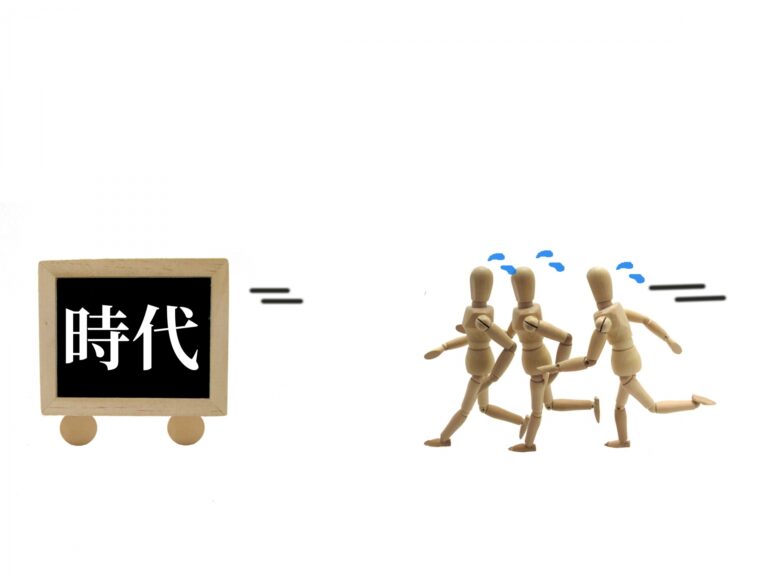

学生さんからよく聞く声として、面接時の面接官の印象が志望度に大きく影響した、というものがあります。昔は自覚があって偉そうな態度を取っていた方もおられたようですが、慢性的な採用難の時代にあっては逃げられてしまいます。採用基準を満たしているか厳しい目でチェックしながらも、感じの良い印象を与える面接をしなくてはなりませんので、慣れないと難しいというのもまた事実かと思います。しかし、慣れてきたら慣れてきたでまた落とし穴があります。
面接官がまだ面接に慣れていないときは、学生さんを見抜くことに一生懸命になりすぎて、感じの良い対応がおろそかになりがちです。学生さんからよく聞く具体的なものとしては、リアクションがない、メモに集中して目を合わせてくれない、無表情、自分に興味なさそう等々です。確かにそういう面接官は良い印象を持てませんよね。しかし面接官に余裕がないと、相手の目に自分がどのように映っているのかにまで気を配るのは難しいと思います。そういう場合は、「面接に慣れていないので実は私も緊張しています。ぎこちないかもしれませんが許してください」などと最初に言ってしまってもいいと思います。
慣れてくると、マンネリに悩むことになります。来る日も来る日も面接をしていても、正直いつも面白い話が聞けるわけではありません。内定率から見ても、不合格になる人の話を聞く方が圧倒的に多いわけです。話題もたいてい、勉強やゼミ活動、サークルや部活、アルバイト、ボランティア、留学、趣味、これでほぼ100%ではないでしょうか。繰り返し同じような話を聞くのですから、常に新鮮なリアクションをしたり、興味を持って聞くのが難しくなってきます。しかも最初の10分くらいで不合格の結論が出ていたとしても、そんなに早く終わらせるのは失礼でもありますので、一通り話は聞くべきとエネルギーを振り絞って聞かなくてはなりません。そういうことが知らず知らずに態度に出て、相手に伝わってしまうのですね。
ということで面接はちゃんとやるとものすごく疲れますので、限られた面接官にばかり負荷がかかると、採用の質が落ちていくことになります。そのためにはやはり学生との接点を増やしていくことが重要になります。少ない点で支えると一つ一つの点に大きな負荷がかかりますが、多くの点で支えることでそれを軽減し、致命的なマイナスを発生させない、もしくは補うことができます。最近では現場の社員も面接官をやるようになったり、リクルーターによる学生フォローも浸透してきました。経営陣の方々も学生との接点を持つことに積極的なケースが増えてきました。こうした全社一丸となった体制づくりと採用活動は今後ますます広まっていくことと思います。
前職は人事を担当。会社全体の仕組みから社員一人ひとりのケアまで、幅広い視点から会社や組織の活性化に貢献します。既存の概念にとらわれることなく、常に柔軟に考えることを心がけています。趣味は料理。食べるのも作るのも大好き!

「採用成功には、採用ターゲットに刺さる自社の魅力を明確にすることが重要です」。正直、耳にタコができるほど聞く言葉です。とはいえ、…


人材獲得競争が年々激しくなる中、「採用マーケティング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。求職者に「選ばれる企業」となるた…

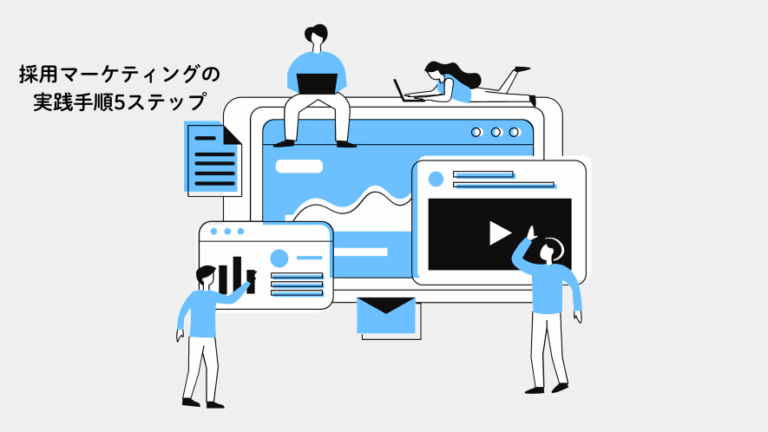
売り手市場が続く採用市場。母集団形成や内定承諾後の辞退は、多くの企業にとって悩みの種といえます。これらの採用課題を解決するために…


ふわっとした悩みから、明確な課題まで。採用力に関することは、何でもお気軽にご相談ください。