パソコンを使えない若者が増殖中

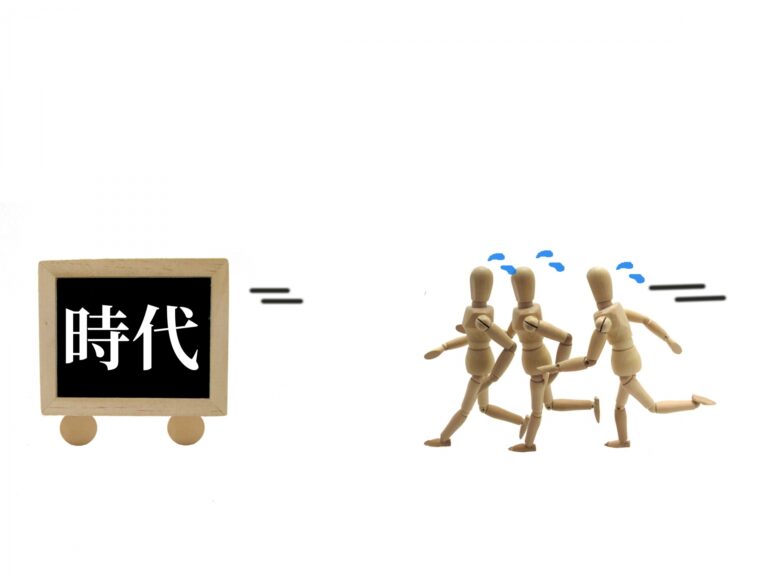
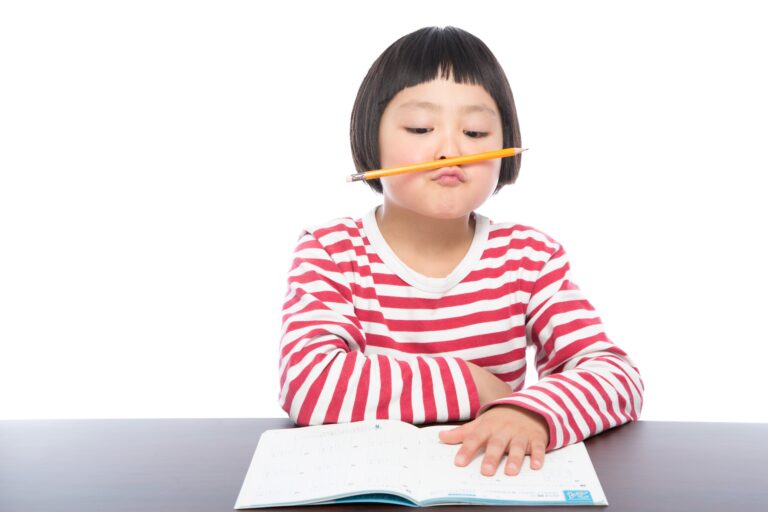
最初はできなかった仕事が、経験を重ねるうちにできるようになり、得意な仕事になり、プロフェッショナルにまで到達する人もいれば、一方でいつまで経っても苦手なまま身につかない人もいます。人間は万能ではありませんから人それぞれに少なからず向き不向きがあると思います。向いているとわかっていれば多少辛くてもがんばれるでしょうし、向いていないとわかっていればそんなものに注力するのは時間も労力ももったいないということになりますが、すぐにはわからないところが悩みどころなのは昔も今も変わりません。特に若い時期はその見極めは難しいですね。ただ一つ確実に言えることは、特に新入社員研修で習うような基本的な仕事の多くは、最初はできなくても経験を重ねるうちにできるようになるということです。できなかった仕事ができるようになるポイントは「ツライとき逃げずにがんばれたか」です。
「石の上にも三年」は老若男女を問わず広く知られたことわざですが、人材の成長という観点でこのことわざを自分事として実感しておられる方は多いのではないでしょうか。右も左もわからないまま無我夢中で過ごす1年目。まだまだ自分のことで精一杯の2年目。ようやく一通りの仕事を覚え、周囲や全体が見えはじめ、自分から仕掛ける余裕が出てくるのは3~4年経った頃。周囲もそろそろ一人前として見てくれるようになります。ここにたどり着くまでに、きっといくつもの「ツライとき逃げずにがんばれた」を経験してきたはずです。
昨今、若者が昔よりもがんばりがきかなくなってきていることが多く取り上げられます。遅刻をとがめたら翌日から会社に来なくなったなど、精神的に弱くなっていることばかり注目されますが、昔よりも転職が一般化したことによる環境の変化などもその後押しとなっている側面も否めません。理由はともかく、3年で3割という言葉に象徴されるように、実態として多くの若者が一人前になる前に会社を辞めて行ってしまいます。もちろん自分なりに悩んだ末に出した結論だとは思いますが、正直もったいないなと感じます。例えばですが、隣の席に「今はツライと思うけどがんばれよ」、「おれもそうだったからよくわかるよ」、「○○さんの資料参考になるから見てごらん」なんて気にかけてくれる先輩がいてくれるだけで全然違うだろうと思います。育成に加えてこのような風土づくりの観点も加えると、また道が開けてくるように思います。
前職は人事を担当。会社全体の仕組みから社員一人ひとりのケアまで、幅広い視点から会社や組織の活性化に貢献します。既存の概念にとらわれることなく、常に柔軟に考えることを心がけています。趣味は料理。食べるのも作るのも大好き!

「採用成功には、採用ターゲットに刺さる自社の魅力を明確にすることが重要です」。正直、耳にタコができるほど聞く言葉です。とはいえ、…


人材獲得競争が年々激しくなる中、「採用マーケティング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。求職者に「選ばれる企業」となるた…

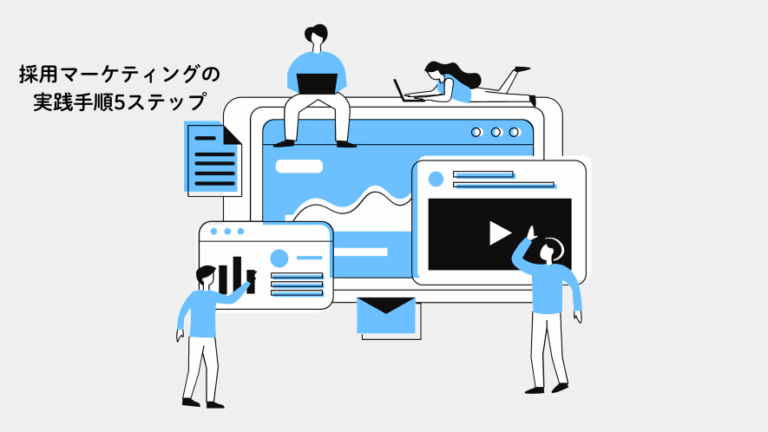
売り手市場が続く採用市場。母集団形成や内定承諾後の辞退は、多くの企業にとって悩みの種といえます。これらの採用課題を解決するために…


ふわっとした悩みから、明確な課題まで。採用力に関することは、何でもお気軽にご相談ください。