パソコンを使えない若者が増殖中

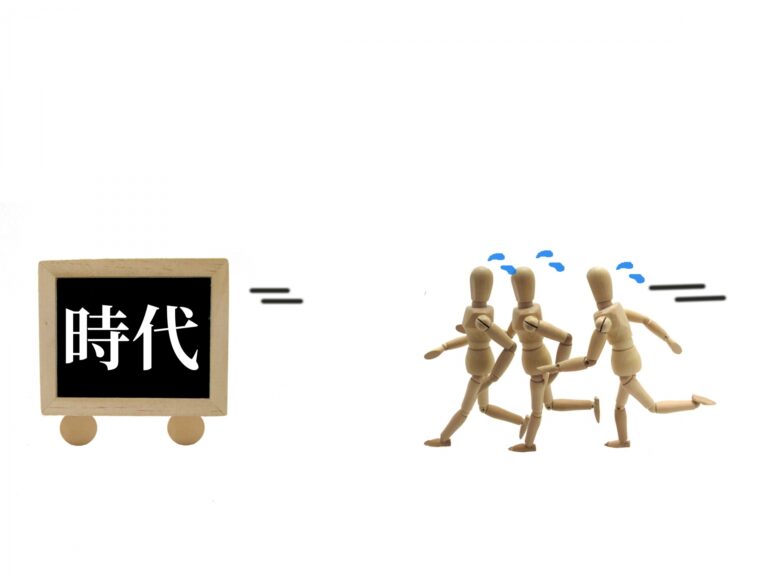

「優秀な社員は優秀な学生から生まれる。優秀な学生とは一流大学の学生である。」
このように考える経営者や人事の方は多いと思います。
しかし、こんな話があちらこちらから聞こえてきます。
「一流大学の学生を採用しているのに成果を出せないのはなぜだ。」
私の知る限り、少なくとも20年以上は繰り返されている話です。
まず大前提として、優秀な学生とそうでない学生では、前者の方が優秀な社員に育つ可能性が高いということ。
また両者ともうまく育ったとして、その優秀さは前者の方が高くなる可能性もまた高いこと。
これは確かにあると思われます。
問題は、優秀だった学生が優秀な社員へと育ってくれる可能性が、期待よりも格段に低いということです。
これはいったいなぜなのでしょうか。
今回はこの問題を考えてみたいと思います。

学生の本分は勉強であることに昔も今も変わりはありませんが、この勉強というものの構造は一言で言えば、「あらかじめ正解が用意された問題に解答すること」と言えるでしょう。
ビジネスの世界も昔はそうでした。
工場で間違いのない物を早く大量に生産することを中心に世の中が回っていた高度経済成長期の時代などはまさに、やれと言われたことを早く正確にできる社員が優秀な社員でした。
言ってみれば、学生と昔のビジネスマンは「顕在化しているニーズに応えること」を求められる存在という点で共通していたのです。
しかし現代のビジネスマンはどうでしょうか。
「言われたことをやるだけではダメ」などという言葉は、新入社員に対しても言われるようになっているように、現代は、まだない新しい価値を提供することが求められる時代に変化してしまいました。
これにともなって、評価の対象も「顕在化しているニーズに応えられるか」から「潜在化しているニーズを掘り起こせるか」へと変化したわけです。
戸惑うのは学生です。
極端な話、誰よりも正解を回答し続けていれば首席を取ることさえ可能だった世界から、急に正解のない世界に放り出されて成果を求められるわけです。
「そんなこと習ってません」というセリフを吐いて、「まったく最近の若者は・・・」と周囲から呆れられる、などというお決まりの構図がありますが、彼らにしてみれば「話が違うぜ」と言いたくなるでしょう。

そういったことに加えて、終身雇用や年功序列が崩れたことで、現場教育がスムーズに伝承されなくなってしまったという組織構造の変化なども重なっています。
このように社会の構造が大きく変化を遂げている中で、教育の構造はなかなか変わらないようです。
この溝が埋まらないうちは、この問題が自然に解決されることはありません。
つまり、いくら優秀な学生といえども、放っておくだけでは育たない時代になっているということです。
解決策はひとつしかありません。
それはズバリ「若手を育てる組織をつくること」。
教育研修体系を整えることももちろん大切ですが、本物のスキルは現場ではぐくまれるもの。
周囲の先輩や上司の積極的な関わりが不可欠です。
そういった風土づくりとともに、若手の面倒を見たり教えたりする社員を大いに評価する仕組みづくりもまた必要になってきます。
前職は人事を担当。会社全体の仕組みから社員一人ひとりのケアまで、幅広い視点から会社や組織の活性化に貢献します。既存の概念にとらわれることなく、常に柔軟に考えることを心がけています。趣味は料理。食べるのも作るのも大好き!

「採用成功には、採用ターゲットに刺さる自社の魅力を明確にすることが重要です」。正直、耳にタコができるほど聞く言葉です。とはいえ、…


人材獲得競争が年々激しくなる中、「採用マーケティング」という言葉を耳にする機会が増えてきました。求職者に「選ばれる企業」となるた…

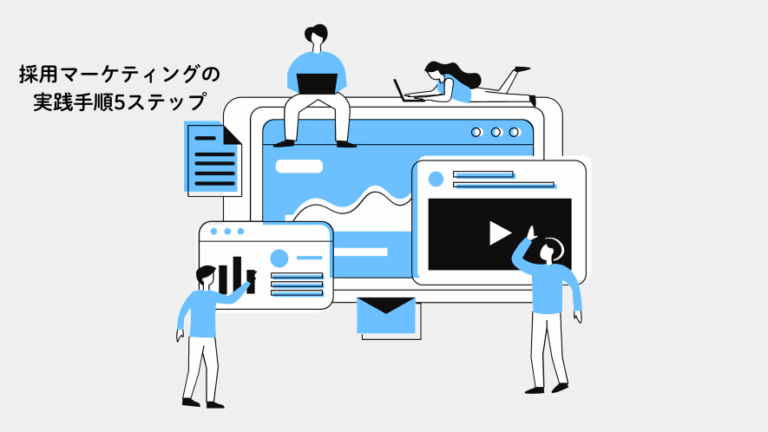
売り手市場が続く採用市場。母集団形成や内定承諾後の辞退は、多くの企業にとって悩みの種といえます。これらの採用課題を解決するために…


ふわっとした悩みから、明確な課題まで。採用力に関することは、何でもお気軽にご相談ください。